*Please note that this page may contain some affiliate links.
※当ブログでは、アフィリエイト広告(リンク)を利用しています。
はじめての精神医学 by 村井 俊哉
ちくまプリマー新書 2021年10月10日
「精神医学について、初めての私でもやさしく理解できるような本が読みたいなぁ」ということで、手に取った本。
と、いうのも。
私には、訳あって以前からずっと読みたいと強く思っている、ある1冊の本がある。⬇️
(その「理由」は、今ここでは割愛……。なおそのことについては、今後このブログへ書くかもしれないし、書かないかもしれない。)
ハーマン『心的外傷と回復』増補新版 2023年10月刊行予定 (msz.co.jp)
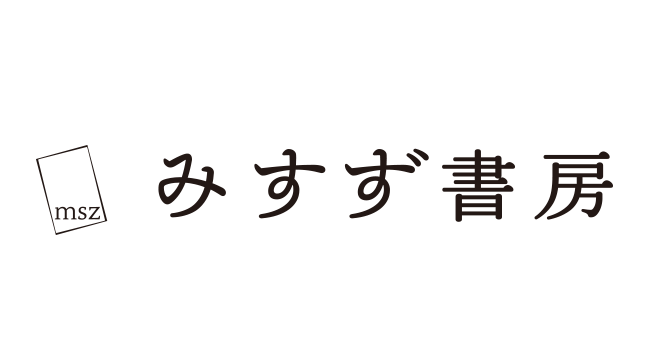
⬆️この本。
(ちなみに私が持っているのは、このオレンジの表紙の⬇️「増補版」だ。
心的外傷と回復【増補版】 | みすず書房 (msz.co.jp)
次の版ではどうやら、「あとがき」と「エピローグ」が追加されるらしい(今知った!)。出版されたときには図書館で借りて、その部分だけでもまた読んでみようかなぁ……。)
図書館で借りることも考えたけれど、やっぱり「自分の本」として読みたくて。付箋も貼ったりしながら、期限付きで焦って読むのではなく、じっくりと腰を据えてよみたくて。だから少ない貯金もはたいて(笑)(結構な値段のする本なのだ……なんと約7000円!)、やっと手に入れて「さあ読むぞ!」と、意気揚々としてページをめくった。
ところが読み始めてすぐに私は、「今の自分にはまだ、この本を読み進める力が足りていないぞ」ということに気がついた。「このままこの本を読むのを強行するのもべつにいいかもしれないけれど、でももう少したくさんのことを知ってから読んだ方が、余計に理解しやすくなるかもしれないなぁ」と、思ったのだ。
それで私は何冊か良さげなものに目星をつけて、それらを先に読んでみることにしたのだ。この本(はじめての精神医学)はその記念すべき(?)1冊目!だ。
どんな本?
「精神医学」という専門分野の全体像を、初心者に向けて伝えてくれる本。
新書ということもあって、コンパクトにまとまっており私もさくさく読めた。「精神医学とは何か?」「どんなものがあるのか?」というようなことについて、考えてみることができる。
気になった箇所の引用
今回の引用箇所は……、少し(かなり?)多くなってしまった。^^;
(本当は、もっともーっとあったんだけれど、ね!これでも絞った方なのだ。えぇ。)
これは、精神科の病気の多くに共通していえることですが、「自分はうまくできる」という自信を持つことは、それで病気そのものが治るわけではなくても、社会生活の困難を減らす方向へと働きます。この「自分はうまくできる」という感覚のことを、心理学の専門用語で「自己効力感」と呼びます。精神科の病気の中には、例えばあとで紹介する双極性障害の躁状態の場合がそうですが、「自分はうまくできる」というこの感覚、つまり自信過剰が失敗につながることもあります。また、精神科の病気の有無にかかわらず、大きな挫折体験は、人生全体を考えたときには大きな糧となることはあります。つまり「自己効力感」は万能ではありません。とはいえ、そうした例外を除き、精神科の病気を持つ多くの人は、病気そのものの症状だけでなく、その病気を持ったことによる様々な困難、例えば受験の失敗、失業、友人関係の破綻、などによって、自分自身の実際の潜在的な能力を低く見積もってしまっていることが多いのです。そういう意味で、「自己効力感」を高めるような働きかけは、精神科の病気を持つ人に対して、多くの場合、大事です。このことをより平易な言葉でいうならば、「ダメ出しするのではなく、よいところをみつけて褒めるようにする」ということでしょうか。「褒める」という言葉には、「自分で自分を褒める」も含まれます。
P44~45
二〇歳台前半に起きることの多い病気ですので、皆さんが小学校、中学校の時期を振り返った時、この病気を持つ同級生に出会う機会はほとんどなかったのではと思います。しかし、この病気は一〇〇人に一人の人にみられる病気です。家族や親戚で、この病気かな、という人がいても不思議ではありません。ところが、これだけ頻度の高い病気なのに、皆さんがこの病気について、私がこの章で述べてきたようなごく基本的なことさえ知る機会がなかったのはなぜでしょうか。その大きな理由は、この病気に対する偏見です。精神科の病気の多くは誤解や偏見の対象になるものが多いのですが、特に、統合失調症は、現在でさえ、偏見の対象となりやすい病気です。偏見が強い病気は本人も家族も、その病気を持っていることを知られないようにします。そのため、つらいとき、助けが必要なときにも、周囲に助けを求めにくくまります。
P54
LGBTについては、どういう状態を病気と考えるのか、それは個人の生き方と考えるのか、という本書の第2部の中心的なテーマに関連して、この半世紀ほどで大きな動きがありました。表1(二八~二九ページ)に現代の精神科の標準的な診断分類のDSM-5を示しましたが、この分類が作成されたのが二〇一三年です。DSM-5の「5」というのは第5版という意味で第1版から順番に改訂されてきて、今に至っているのです。そのうちの第3版であるDSM-Ⅲが出版されたのが一九八〇年です。このとき、それまでは病気とみなされていた同性愛、つまり、レズビアンとゲイが、精神科の病気から除外されました。これらの状態を病気から外すことを望んだのは、同性愛者自身でした。
P109~110
しかし、本人が強い苦痛を感じるのは、本人の問題というよりは、社会がトランスジェンダーという生き方に不寛容であるからだ、という考え方はできないでしょうか。本人が強い苦痛を感じているとしても、それは「病気ではない」としてしまって、むしろ、社会の側を変えるべきではないか、という考えも成り立ちます。先ほど性別の三つの意味を紹介しましたが、今までは第一の意味の性別、つまり生物学的性別と、第三の意味の性別、つまり性別役割がほぼ同じものとして扱われてきました。もし、性別役割がもう少し柔軟なものであれば、それと性別意識との不一致で、本人が強い苦痛を感じることも少なくなれば、性別違和という病名自体が本当に必要なのか、ということになってきそうなものです。
P111~112
こうした中、こちらも国際的に広く使われているWHOによるICDという診断基準の第一一版(二〇一八年発表)では、性同一性障害自体が精神科の病気から外されることになったのです。
このような流れをみていますと、精神科の病気の範囲は、精神医学の中だけで考えていてもどうなるものでもなく、社会がその状態をどう考えるか、ということと連動していることがわかります。LGBT法案の成立もそうですが、社会の側が、トランスジェンダーと呼ばれている人たちにとってとげとげしいものではなく、暮らしやすいものとなれば、性別違和の存在意義も乏しくなっていく、ということになります。
「病気とは何か?」、「医療とは何か?」ということを考えるとき、常識的に考えると、「病気とは何か?」ということが先に決まっていて、それに対応して、治療法を開発したり実際に治療をしたりするのが医療(つまり、医師や看護師、病院や診療所)である、と考えますよね。新しい病気が登場して、現時点でまだ治療法がなければ、医学研究者は新しい治療法を生み出すべくさらに努力をします。こうした努力を続けることで、医療・医学は進歩してきた、というイメージです。つまり、「病気」と「医療」の間の関係の、常識的なイメージは、「まず「病気」というものがある。それに対して「医療」が対応する」ということです。(中略)
P181~183
ところが、このあたり前の発想が、病気の中でも、特に「こころの病気」について考える場合には、うまくいかなくなることが多いのです。
たとえば、第4章で紹介した社交不安症の場合、ひと昔前であれば、「人前であがりやすい体質」ぐらいに思われていて、これを病気であるなど考えてみてもいまかった人も多かったはずです。ところが、その「人前で上がりやすい体質」を楽にしてくれるような薬が発見されました。「治療法があるのなら」治療してもらった方がそれは楽だよね、治療できるということなら「病気」という理解でよいのでは、と人は考えるようになってきたのです。
ひと昔前であれば、家族の死で気分が落ち込んでいるとき、「その悲しみは深くまた長くても、ご家族とお別れする大切な儀式なんですよ」と考えてきた人は多かったでしょう。ところが、「抗うつ薬で気分の落ち込みはかなり楽になりますよ」ということになると、「治療法があるのなら」、こうした状態も病気と考えた方が自然だよね、という発想になってくるのです。
つまり、病気と医療の間の関係の、ちょっと意外なイメージは、「医療が対応できる状態がある、それに応じて「病気」の範囲が決まっていく」ということになります。「医療が先で病気が後」ということです。「病気が先で医療が後」という常識的な理解とは逆、ということになります。
※太字箇所も全て、書籍中の文章をそのまま引用したもの。
感想と思考
この本を読んだことで「変わったな」と感じる、自分の考え方がひとつある。それは「病気」は必ずしもいつも、それ単独で成り立っているわけではないんだな、ということだ。
今までの私が「病気」や「医療」と聞いて想像するものと言えば、目に見えるふうなもの(例えば風邪だったり怪我だったり)が主だった。そしてそれらは普通、その「病気」だけで成立している。べつに私にはお医者さんのような医療的な知識なんてないけれど、でも例えば今この歯を治さないといけない理由は虫歯になっているからなんだなとか、骨折したのは自転車から落っこちてしまったからなんだなとか、そういったことくらいなら理解できる。
誰が見てもその虫歯は虫歯でしかないし、「どうしてこの骨が折れたんだっけ?」と聞けば、みんな「自転車ごと転けたからでしょ」と答えるはずだ。いつどこでどんな人が診たとしても、それが「病気」であることには変わりはない。今までの私は、「病気」と言えば全てそういうものなんだと思っていた。でもこの本によると……どうやらその考えは、少し違っていたらしい。
「こころ」の状態は、目には見えない。だから私はこの本を読むまでは実は、「精神医学って、いちばん『内側』に位置する医療なのかな。だってよく見える外側……例えば手足の傷だったり体内の臓器だったり、そういったものを直接治療するわけでは、基本的にはないはずだもの。」というふうな考えを持っていた。
でもそんな意見も、この本を読んだことで変わった。
「いちばん『外側』のもの、つまり『社会』と最も近い場所にある医療、それが『精神医学』なのではないか?」
とか、
「奥底にある、簡単には見えないもの(=心)を取り扱うのに、それでいて誰もが接する権利のある、表にあるもの(=社会)とも密接に関わっている、『精神医学』とはつまりそういうものなのではないか?」
だとか。
そんなふうに、思うようになったのだ。
社会のしくみに、哲学。考え方、それに人々の物事に対する認識。どれだけの知識や理解が、1人ひとりに備わっているのかどうか。
そういったたくさんの要素が複雑に絡み合いながら、時代や地域、社会の移り変わりと共に絶えず変化していくもの、それこそが「精神医学」なんじゃないかなぁ……、なんて。この本を読んで、思ってしまったのだ。
見えないもののことを考える、って、もしかしたらものすっごく面白いこと、なのかもしれない。
この本は今の私にとって、そんなふうに思わせてくれた1冊だった。
もっともっと、たくさんのことを知りたいな。体験したいな。
見たいな。聞きたいな。考えたいな。感じたいな。
P.S.
本書を読んで精神医学に興味を持たれた方は、ぜひ、他の著者の本も読んで見てください。いくつかの本を読み比べていくうちに、次第に、読者の皆さん自身の意見を持つことができるようになってきます。そして、その意見を、誰かの受け売りではなく、自分自身の意見として持つことができ、さらには、自分とは異なる意見もありうる、と考えることができるようになります。そこまでいけば、精神医学についての理解は相当なところまで深まったということができるでしょう。そうなれば、今の精神医学についてそれがおおよそどのようなものかが理解できているだけでなく、これからの精神医学がどうあるべきか、自分自身の意見を持つことができるようになっているでしょう。
P18
……ということらしいので(ちなみに私も、筆者のこの意見には大いに賛成!)。現在は2冊目として、下記⬇️の本を読み始めているところだ。やっぱり、面白い!知ることって、考えることって、こんなにも楽しいことだったんだ……、ね。(^-^)/



